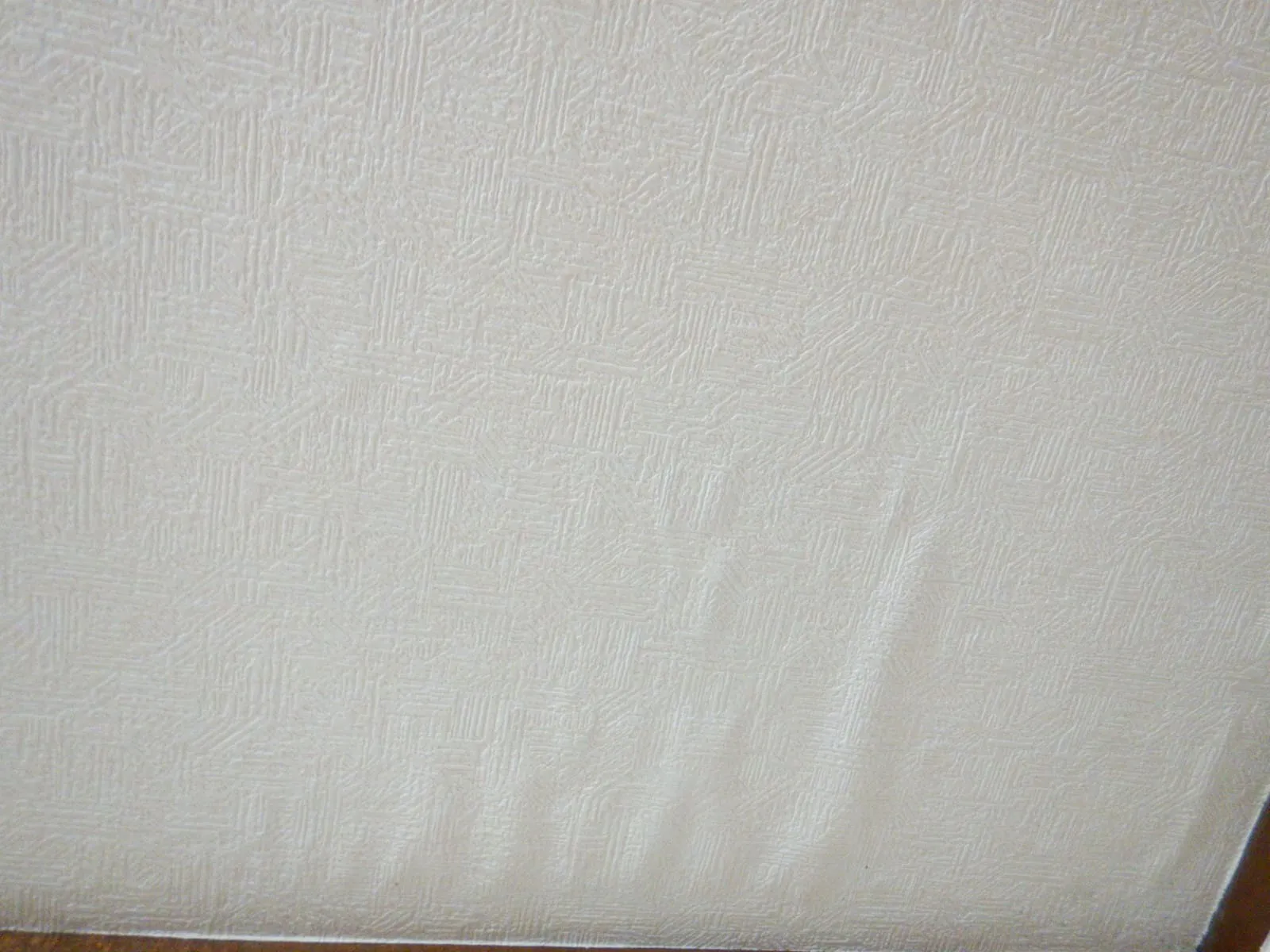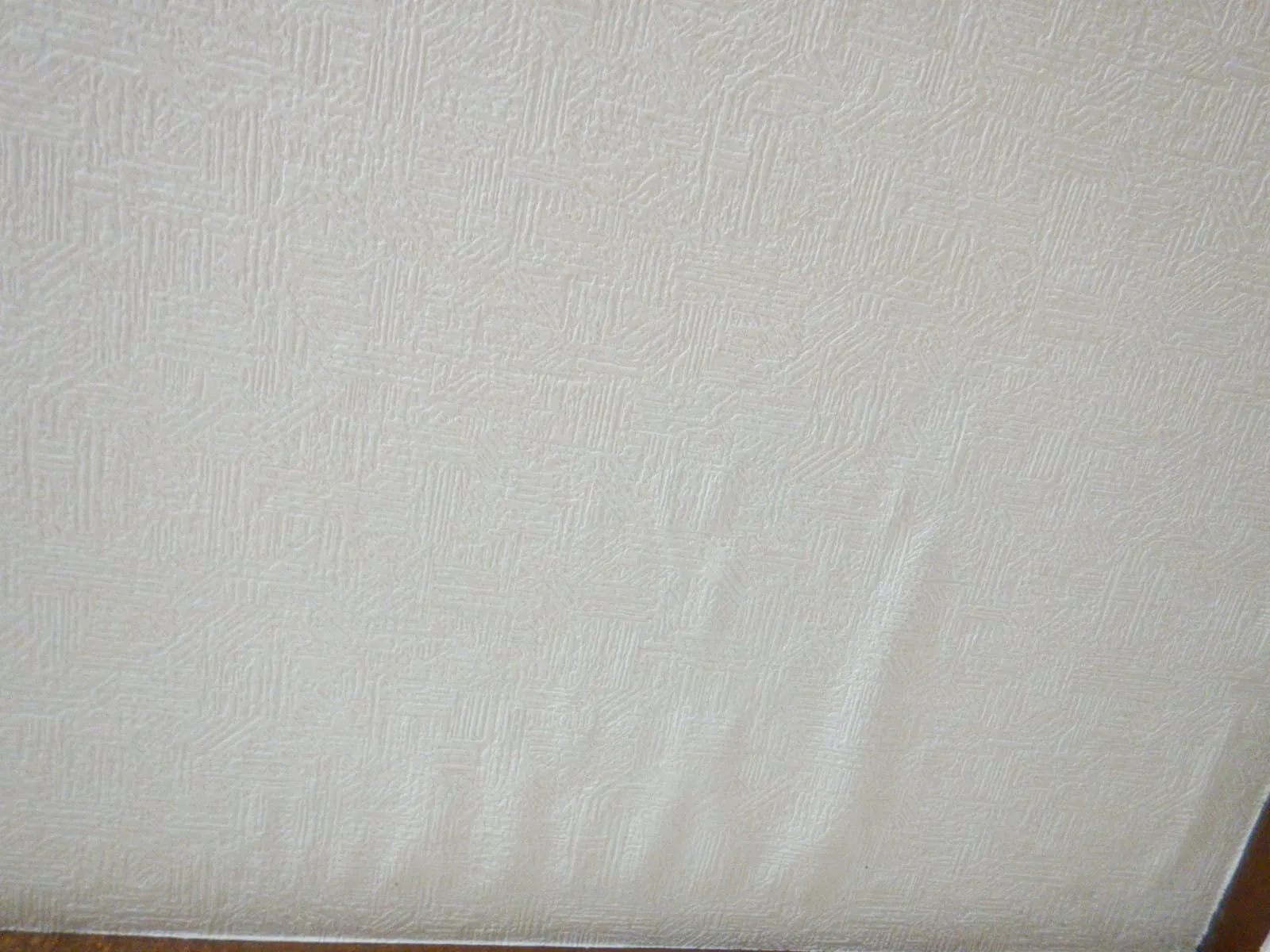壁紙張替え防カビ工事の限界|結露を止めなければカビは止まらない
2025/11/11
結露がカビを繁殖させる事実
冬の室内で発生するカビの多くは、結露が原因です。
特にコンクリート直張り壁紙では、表面の温度が下がりやすく、壁紙の裏側で湿気が滞留します。
この“見えない結露”が、黒カビを繰り返す最大の要因です。
■ かつての施工:壁紙張替え防カビ工事
2020年2月、分譲賃貸団地の一室で防カビ工事を行いました。
築年数が経過した建物で、外壁側のアルミサッシにはカバー工法が採用されており、断熱性能が下がっていたため、サッシまわりに大量の結露が発生していました。
当時は、壁紙を剥がして下地のカビを除去し、殺菌消毒・防カビ施工を経て仕上げるという、いわば「壁紙張替え防カビ工事」の完成形でした。
しかし、今振り返ると──
この工法には明確な限界があります。
それは「結露そのものを止められない」という構造的な問題です。
■ 工事前の様子:壁紙裏まで広がったカビ
以下の写真は、施工前・施工中・施工後の様子です。
結露によって壁全体にカビが発生し、
下地(コンクリート直張り構造)まで浸食していました。
※以下の写真は、2020年当時の現場記録です。
6年が経過した今、あらためて振り返ると
“壁紙張替え防カビ工事”の限界を実感できる事例といえます。
過去の工事事例

カバー工法の結露は止まらない
カビは発生する条件があります。
中でも結露や高い湿度はカビ繁殖の最大の原因になります。
この状況を改善するには、結露防止テープなどを枠に貼ったり、「住み方の工夫」をするなどの対策が望まれます。

コンクリート直張り壁紙の結露でカビ繁殖は加速する
カバー工法の結露とコンクリート直張り壁紙の結露のダブルで結露によるカビは一気に増大し、繁殖を繰り返します。
その結果、壁コンクリート下地が劣化することを忘れてはいけません。住む人の健康だけでなく住まいも劣化するのです。
■ 量産品壁紙の限界
この現場では、予算の関係で量産品(普及品)壁紙を採用しました。
一般的な壁紙でも仕上げとしては十分に美しいのですが、
吸放湿性能がほぼゼロに近く、結露環境では再発リスクが残ります。
防カビ工事の効果を長く維持するためには、
「吸放湿性」のある機能壁紙を選ぶことが理想的です。
問題は、壁紙裏の紙です。(裏打ち紙とも裏紙とも言います)
紙の部分に結露が浸透するとカビが繁殖してしまいます。
そうならないためにも、吸放湿壁紙張りを強くおすすめしています。
吸放湿壁紙には若干ですが、吸放湿してくれる吸水性ポリマーが入っており、コップ6杯分の湿気を吸収・放出してくれます。ここが量産品壁紙との違いです。
■ 進化:防カビ結露対策工事へ
この経験を経て、プレモでは現在、「防カビ結露対策工事」を標準施工としています。
カビを止めるだけでは不十分。
結露を抑えなければカビは止まらない。
防カビ結露対策工事では、
カビ取り・殺菌消毒・防カビ施工のあとに、
結露対策用シート(防湿・断熱材)を貼り、吸放湿壁紙で仕上げます。
湿度変化に対応し、壁内結露の発生を抑制する工法です。
■ まとめ
「カビを止める施工」から「現象を止める施工」へ。
プレモは、過去の経験から生まれた課題を検証し続け、今の技術に進化させてきました。
20年行って来た防カビ工事でカビの発育阻害環境を作り、
結露対策用シートでカビを繁殖させる結露を抑止する二段構えです。
防カビ工事で見えるカビを止め、
防カビ結露対策工事で“再発しない環境”をつくる──
それが、プレモの考える「結露とカビに強い住まい」にすることです。
👉 結露関連ブログはこちから。【埼玉・東京】結露する壁コンクリート下地の断熱工事はどちらが良い
👉 天井コンクリート直張り壁紙の結露カビの関連ブログは、こちらをご覧ください。
👉 天井結露とカビなら、こちらを参照ください。(賃貸大家さん向けに書いています)
----------------------------------------------------------------------
有限会社プレモ
〒362-0062
埼玉県上尾市泉台3-17-28
電話番号 : 048-793-7148(担当:山田)
----------------------------------------------------------------------