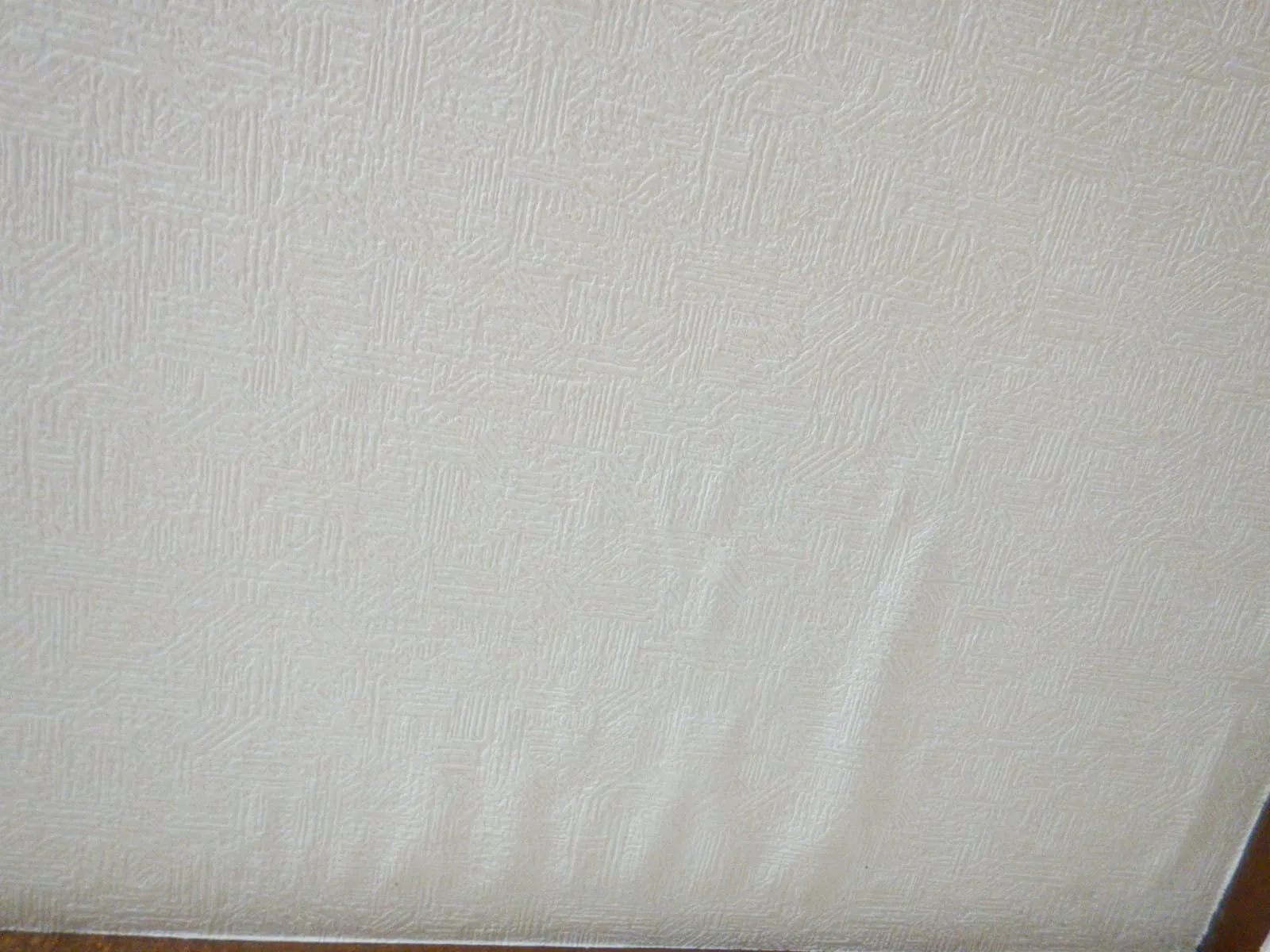建築中に雨で濡れた構造用合板|乾いたあとに始まる腐朽菌の危険
2025/11/07
雨に濡れる合板・木材
新築の建築現場を見に行ったとき、床や柱が雨で濡れていた──
そんな光景を見たことがある方も多いと思います。
「自然乾燥すれば問題ない」と説明されることもありますが、その“乾いたあと”こそ、本当の危険が始まることをご存じでしょうか。
雨に濡れた木材は「乾けば安全」ではない
建築中の木材や構造用合板は、長時間の湿潤にさらされると、
内部にまで水分が浸透し、真菌(カビ)や腐朽菌の発芽条件が整います。
表面が乾いても内部の湿気は残留し、やがて湿度と温度が上がると再び活動を始める──それが“休眠菌”の怖さです。
カビ・灰汁・腐朽菌の連鎖
木材は、雨に濡れるとまず「灰汁(あく)」が浮き出ます。
灰汁そのものに健康被害はありませんが、カビの呼び水になります。
ですから、灰汁(あく)を軽視してはいけないのです。
カビが繁殖すると、菌糸が木材内部へ入り込み、さらに奥で腐朽菌(木材を食べる菌)が発芽。
この連鎖が進むと、構造用合板の強度が低下し、住宅の寿命を縮める原因になります。
床下の“静かな進行”
とくに基礎内断熱工法を採用した住宅では、床下に湿気がこもりやすく、乾燥しにくい構造になっています。
その結果、施工直後から床下合板にカビが発生するケースも珍しくありません。
見た目には何も起きていないようでも、合板内部ではカビと腐朽菌が静かに進行している場合があります。
📷はイメージ画像です。
雨に濡れた構造用合板です。建築中大雨が降るとこんな感じになります。
構造用合板が雨を吸い込んでしまうこともあります。
プレモの立場:構造を守るための防カビ工事
プレモは、こうした「見えない進行」に対し、カビ取り → 殺菌消毒 → 防カビ施工を基本とし、木材内部の菌密度を下げて再発を抑止します。
単なる表面塗布ではなく、構造を“再生”する意識で防カビ工事を行うのが特徴です。
まとめ
建築中の雨は避けられません。
しかし、乾いたからといって「もう大丈夫」とは限りません。
湿気と菌の条件が整えば、カビだけでなく、腐朽菌はいつでも再発します。
防カビ工事は、表面から3mm近く薬剤を浸透させ、バリアを張りカビや腐朽菌から住宅を守るための“構造の予防接種”です。
----------------------------------------------------------------------
有限会社プレモ
〒362-0062
埼玉県上尾市泉台3-17-28
電話番号 : 048-793-7148(担当:山田)
----------------------------------------------------------------------