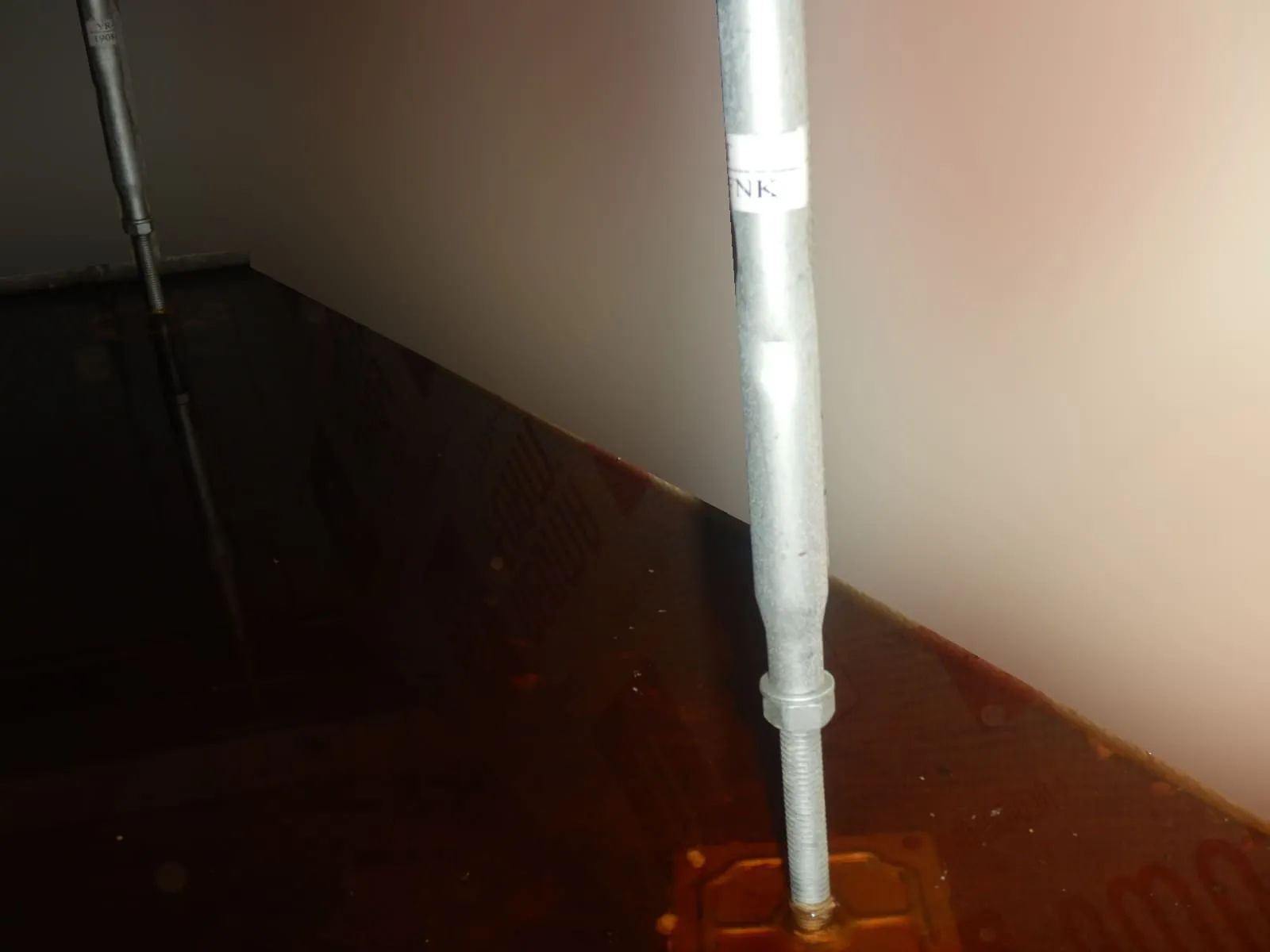【2024年問題と新築住宅のカビリスク】工期延長が招く隠れた脅威と防カビ対策の重要性
2025/08/01
工期延長とカビリスク
皆さん、こんにちは!埼玉県上尾市で防カビ工事専門業者20年の実績を持つプレモの山田です。
最近、建築業界では「2024年問題」をはじめとする様々な課題が浮上しています。時間外労働の規制強化、それに伴う工期の延長、資材や人件費のコストアップ、中小企業の倒産増加、そして深刻な人手不足…。これらの問題は、新築住宅の建設にも大きな影響を与え始めています。
特に、地場の工務店が手掛ける注文住宅において、「工期の延長」が避けられない状況になりつつあると懸念されています。この「工期の延長」は、実は住宅の品質、特にカビの発生リスクと密接に関わってくることをご存知でしょうか?
「工期を縮める工夫をしているのに、カビ対策のために工期を延長するなんて考えられない」「そんなことを言われても納得できない」――そう思われる工務店様もいらっしゃるかもしれません。しかし、これは目先の工期と、長期的な住宅の品質・コストという、異なる視点から考えるべき重要な問題です。
今回は、建築業界の現状が新築住宅にどのようなカビリスクをもたらすのか、そしてその対策として何が重要なのかを、専門家の視点からお話ししたいと思います。
建築業界の「2024年問題」が新築住宅に与える影響
2024年4月から適用された時間外労働の規制は、これまで長時間労働に依存してきた建築業界に大きな変革を迫っています。これにより、以下のような影響が顕著になりつつあります。
1. 工期の延長:職人の労働時間に上限が設けられることで、これまでのような短期集中での工事が難しくなり、全体の工期が長期化する傾向にあります。
2. 人手不足の深刻化:賃金アップや労働環境改善が進まなければ、若年層の入職はさらに減少し、熟練職人の引退も相まって、人手不足は一層深刻化するでしょう。
3. コストアップ:人件費の増加や、工期延長による間接費の増大は、最終的に建築コストに跳ね返ってきます。新築住宅は、原材料と工期延長による職人のコストアップなどがあり、今までの1.5倍近い金額になる可能性を秘めています。
4. 中小工務店の経営圧迫:大手ハウスメーカーは体力がありますが、中小の工務店はこれらの変化に対応しきれず、廃業や倒産に追い込まれるケースも増える可能性があります。
このような状況下では、新築住宅の建設、特にきめ細やかな対応が求められる注文住宅において、工期の延長は避けられない現実となりつつあります。
ひどい時は建築中の住宅を途中で投げ出す建築会社もいます。契約する際は慎重に検討されることを希望しております。
工期の延長が「カビ発生しやすい環境」を招く恐ろしさ
プレモが最も懸念しているのは、この工期延長が、新築住宅の「カビ発生リスク」を著しく高めるということです。
住宅の骨組みや断熱材、内装材などが雨風にさらされる期間が長くなればなるほど、建材が湿気を吸い込む機会が増えます。
・雨天時の影響:建設途中の建物は、まだ完全に密閉されていないため、雨が降れば内部に水が浸入しやすくなります。工期が延びれば、この「雨ざらし」の期間が長くなり、木材などの建材が繰り返し濡れて乾燥しきらない状態が続くリスクが高まります。
・湿気の滞留:建物がある程度の形になってくると、内部の通気が悪くなり、湿気がこもりやすくなります。特に、梅雨時期や夏場の高温多湿な時期に工事が滞ると、カビが繁殖しやすい環境が整ってしまいます。
・乾燥不足:建材が十分に乾燥しないまま次の工程に進んでしまうと、壁の内部や床下など、目に見えない場所でカビが密かに繁殖を始める可能性があります。一度カビが根を張ってしまうと、完成後もカビ臭がしたり、健康被害の原因となったりする「不健康な住宅」になってしまうのです。
・基礎断熱工法特有のリスク:基礎断熱工法は、基礎の内側で断熱を行うため、床下空間が室内環境の一部として扱われます。しかし、この工法において適切な湿気対策や換気がなされないまま工期が延びると、床下で発生したカビが、構造用合板に設置予定の通気口(点検口や配管口など)の隙間を通じて室内に流入し、住む人の健康を害する可能性が高まります。特に、建築中に床下が湿気にさらされた場合、その影響は完成後も続き、見えない場所でカビが繁殖し続けるリスクを抱えることになります。
「新築だからカビの心配はないだろう」という常識は、もはや通用しない時代になりつつあると言えるかもしれません。
建築中住宅で見られるあり得ない光景
お客様(施主)は知っているか知らないか分かりませんが、建築中住宅が雨に濡れると見たことがない光景が床下や構造用合板(フローリング下地材)にカビや灰汁が発生してしまうことがあります。
防カビ工事専門業者として20年の経験から少しだけそのあり得ない光景をご紹介します。
雨に濡れた構造用合板のカビ
大手ハウスメーカーと地場の工務店、それぞれのカビリスク
前述の通り、2024年問題がもたらす建築業界の現状は、新築住宅の供給構造に大きな影響を与える可能性があります。
・大手ハウスメーカーへの集中:資金力や人材確保力のある大手ハウスメーカーに新築住宅の需要が集中する可能性があります。しかし、大手だからといってカビリスクがゼロになるわけではありません。大量生産・画一的な工法の中で、湿気対策や乾燥工程が疎かになるリスクは常に存在します。
・地場の工務店の注文住宅:地場の工務店は、地域に根ざしたきめ細やかな対応や、自由度の高い注文住宅が魅力です。しかし、2024年問題の影響をより強く受け、工期延長や職人確保の課題に直面しやすいのも事実です。これにより、建材などの養生を行っても意図せず建材が湿気にさらされる期間が長くなり、カビ発生のリスクが高まる可能性があります。
どちらの選択肢においても、「カビ対策」という視点での品質管理が、これまで以上に重要になってくるでしょう。
新築住宅だからこそ、防カビ対策は「初期投資」と考えるべき:工務店様への提言
「工期を縮めたいのに、なぜカビ対策のために時間をかける必要があるのか?」そうお考えの工務店様もいらっしゃるかもしれません。しかし、新築住宅における防カビ対策は、単なる「工期延長」ではなく、「将来的なトラブルとコストを回避するための、極めて重要な品質確保の工程」であるとプレモは考えます。
むしろ、完成後にカビ問題が発覚した場合の修繕費用や健康被害のリスクを考えれば、建築段階での適切な防カビ対策は「必須の初期投資」と捉えるべきです。 これは、大手ハウスメーカーが「糠に釘」となりがちな、目先のコスト削減を優先する姿勢とは一線を画し、地場の工務店様が「健康な住まいづくり」で差別化を図る大きなチャンスでもあります。
・「見えないコスト」の回避:カビを放置・不適切な処理をした結果、何故防カビ対策をやらないといけないのか? カビを放置したり、安易な方法で不適切なカビ処理(例:表面的な拭き取り、市販品の使用、専門外業者による不十分な施工など)をした場合、目先の費用は抑えられても、結果として以下のような深刻な「見えないコスト」が発生します。
〇健康被害の悪化と長期化:カビは目に見えない胞子やカビ毒を放出し続け、アレルギー症状(鼻炎、喘息、皮膚炎など)や呼吸器疾患を悪化させ、特に小さなお子様や高齢者の健康を著しく損ないます。放置すればするほど症状は慢性化し、医療費の増大や生活の質の低下に繋がります。
〇建物の構造的ダメージと大規模修繕:カビは建材(木材、石膏ボードなど)を腐食させ、建物の耐久性を低下させます。放置すれば、床のきしみ、壁の軟化、シロアリの誘発など、最終的には壁の解体や大規模な構造補修が必要となり、当初の建築費用をはるかに超える高額な修繕費用が発生します。
〇物件価値の著しい低下と再販・賃貸の困難化:「カビの生えた家」という事実は、工務店のブランドイメージを著しく損ない、口コミや評判を通じて新たな顧客獲得を困難にします。
〇精神的ストレスと生活の質の低下:カビの存在やカビ臭は、住む人にとって常に精神的なストレスとなり、快適な住環境を奪います。「どうせまた生える」という諦めは、日々の生活の質を著しく低下させます。
プレモの防カビ工事がもたらす価値:プレモが行う防カビ工事は、カビの発生を強力に抑止し、長期にわたって健康で快適な住環境を維持するための専門的な対策です。
〇建材への徹底的な殺菌消毒:建設途中の建材が湿気を吸い込んでしまった場合でも、カビが根を張る前に徹底的に殺菌消毒を行います。
〇安全性の高い防カビ施工:人体に安全な「非流出性複合抗菌剤」を塗布することで、カビが繁殖しにくい環境を作り出します。これは、カビの栄養源となる腐朽菌の繁殖も抑止することに繋がると考えています。
〇見えない場所への配慮:特に、床下や壁の内部など、完成後には見えなくなる場所こそ、プロの目で徹底したカビ対策を施すことが重要です。
注文住宅の施主様へ:ご自身の目で「見えない場所」を確認する重要性と費用について
建売住宅では建築プロセスへの関与が難しい側面がありますが、注文住宅の施主様には、ご自身の目で「見えない場所」の状況を確認していただくことを強くお勧めします。大手ハウスメーカーのような「圧力」がない地場の工務店であれば、施主様が直接確認を求めることも比較的しやすいはずです。
新築住宅における工事中のカビ発生は、施主様からすれば「あり得ない」と感じるでしょうし、その費用は建築会社が負担すべきだと考えるのが妥当でしょう。しかし、プレモでは、工事代金は施主様から直接頂戴する方針を一貫させております。 これは、建築会社との間で支払いに関するトラブルや減額交渉が発生するリスクを避けるためです。
そのため、施主様には、「最終支払い金から防カビ工事代金を差し引いた金額を建築会社にお支払いください」と事前にお伝えし、「事前に建築会社とこの点についてしっかり話し合いをしてください」と強くお勧めしております。この事前確認と合意が、後々の不要なトラブルを避けるために非常に重要です。
【プレモの支払い方針と建築会社様への対応について】
過去に建築会社からの依頼で建築中注文住宅の防カビ工事を行った際、建築会社とトラブルになり裁判沙汰になったことがあります。その教訓を生かして下記の通り対応することにしています。
プレモでは、過去に2度、工事代金をお支払いいただけず、やむなく裁判に至った経験がございます。
➊ 「困っているからすぐにやってほしい」といったご要望であっても、安易にお引き受けすることはございません。
❷ 特に、見積書を作成しても何も言わずに「やってくれ」と急かすような建築会社様は、後々のトラブルに繋がりやすいため、最も慎重に対応させていただいております。
建築会社様からのご依頼の場合:原則として工事前に工事代金のお振込みを確認後に作業を開始いたします。または、工事完了後1週間以内のお振込みのみに対応させていただいております。
また、建築会社様の担当者様とのお話の中で、話の成り行きがうやむやになりそうだと判断した場合は、お客様にご迷惑をおかけすることを避けるため、すべてお断りさせていただいております。
施主様からのご依頼の場合:建築会社との付き合いはありませんので、施主様から防カビ工事代金のお支払いを頂戴するようになります。詳細は施主様に直接プレモがお話ししています。
プレモは、お客様への確実なサービス提供と、健全な事業運営のため、この方針を一貫させております。
施主様が建築会社に言うべきこと・やるべきこと
➊ 床下の状況確認:建築途中、特に基礎工事が完了し、床下の木材が組まれた段階で、一度ご自身の目で床下の状況を確認してみてください。湿気がないか、不自然な水たまりがないか、木材にカビの兆候がないかなどをチェックしましょう。※特に床下の点検は何度やってもおかしい話ではありません。
❷ 工務店への質問:カビ対策について、工務店がどのような対策を講じているのか、具体的に質問してみましょう。特に、雨天時の養生や、湿気対策、乾燥工程について確認することが重要です。工事請負契約書にカビについての記載が無いことを理由に返答しないようなことがあれば、その建築会社との契約は見直すべでしょう。
❸ 専門家への相談:もし少しでも不安を感じたら、迷わずカビ対策の専門家であるプレモにご相談ください。プレモは、第三者の視点から客観的に状況を診断し、適切なアドバイスや対策をご提案いたします。新築だからこそ、後悔のない「健康な住まい」を手に入れるために、プロの知見をぜひご活用ください。
無料相談のご案内:新築住宅のカビリスク、不安を抱え込まず、今すぐプレモへご相談ください!
「新築を計画中だけど、カビが心配…」
「工務店選びで、カビ対策についてどこまで聞けばいいか分からない…」
「健康で快適な住まいにしたい!」
どんな新築住宅のカビに関するお悩みでも、プレモがお力になります。
専門家による無料相談で、あなたの新築住宅がカビのない、健康で快適な未来を築きましょう。
【対応エリアについて】
プレモの防カビ工事は、確実な効果と丁寧なアフターフォローを提供するため、対応エリアを限定させていただいております。
埼玉県(県央・県南・県西・県東地域)および埼玉県に隣接する東京都の地域を主な対応エリアとしております。埼玉寄りの千葉・東京寄りの神奈川にも対応可能です。
遠方地域へのご依頼は、サービスの品質維持のため、現在承っておりません。何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
----------------------------------------------------------------------
有限会社プレモ
〒362-0062
埼玉県上尾市泉台3-17-28
電話番号 : 048-793-7148(担当:山田)
----------------------------------------------------------------------