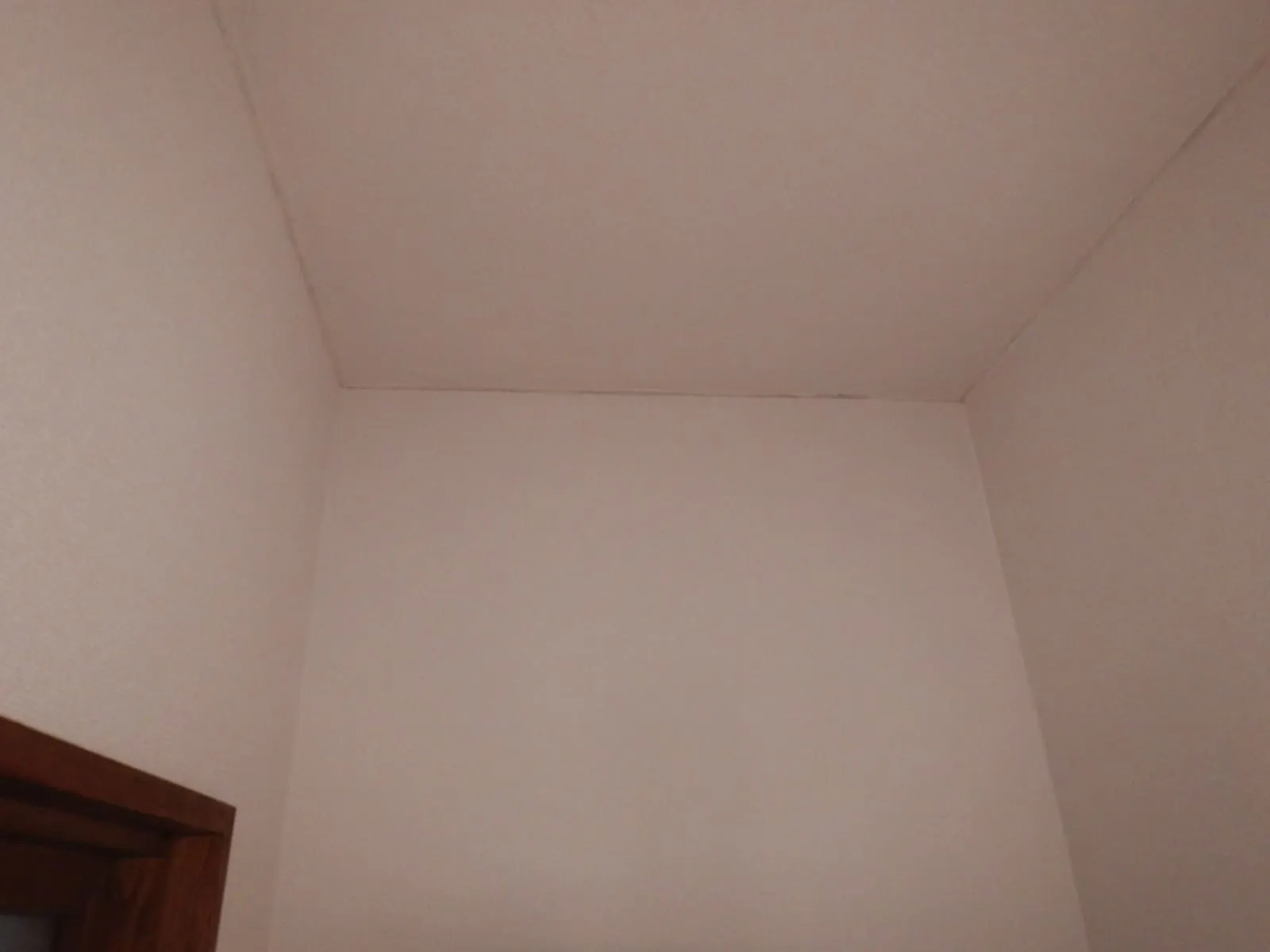【上尾市】浴室ドア開けっぱなしは壁紙カビの温床に|防カビ結露対策工事と住み方の工夫
2025/10/26
■浴室ドア開けっぱなしではありませんか?
小さなお子さんがいるご家庭や、湿気の多いマンションでよく見られるのが、「お風呂のドアを開けっぱなしにする」という習慣です。
入浴後の熱気を逃がすつもりで開けている方が多いのですが、実はこれが「洗面所のカビ被害」を生むきっかけになります。
■気づかないうちに広がる“湿気ルート”
浴室の暖かく湿った空気は、ドアを開けることで一気に洗面所に流れ出します。
洗面所の壁や天井の一部は外壁面に面していることが多く、そこに冷えた空気がぶつかることで結露が発生。
壁紙の裏側では、見えないうちに黒カビ(クラドスポリウム属など)が繁殖します。
さらに時間が経つと、石膏ボード下地が湿気を吸って軟化し、指で押すとへこむような状態にまで悪化することもあります。
■湿気は“空気の流れ”で動く
浴室→洗面所→廊下という空気の流れができると、湿気が廊下や寝室の方へも運ばれてしまいます。
特に冬場、洗面所が冷えた状態で浴室ドアを開けると、湿気が冷たい壁にぶつかって筋状カビを発生させます。
下の写真(杉並区の事例)は、まさにその典型です。
浴室ドア開放+換気不足で壁紙の裏までカビが進行し、防カビ工事で下地まで処理する必要がありました。
■洗濯機まわりは“湿気の吹き溜まり”
洗面所でカビが最も多いのが、洗濯機の裏側です。
ここは空気が動かないため、いったん湿気がこもると長時間滞留します。
浴室ドアの開けっぱなしで流れ込んだ水蒸気と、
洗濯時の湿気が合わさることで、カビが壁紙の裏まで根を張ります。
防カビ工事では、表面だけでなく壁紙を剥がし、下地を殺菌消毒してから防カビ処理を行います。
洗面所のように人の出入りが多い場所では、再発リスクを減らすことが最重要です。
■コンクリート壁+石膏ボード天井は要注意
上尾市内のマンション洗面所では、事例としては少ないですが、コンクリート直張り構造の洗面所も存在します。(これは賃貸を含みます)
一般的には、石膏ボード下地に囲まれた洗面所が多く、こうした構造では、結露や湿気の滞留によりカビが発生しやすくなります。
この構造では、外壁面の冷却による結露と、天井の湿気滞留が重なり、壁と天井の両方にカビが発生するケースが多発します。
文京区で行った洗面所の防カビ結露対策工事では、カビ取りと殺菌消毒の後、防カビ剤を含んだ下地処理を行っています。(本来は、コンクリート直張り壁紙に防カビ結露対策工事を行います)
■住み方の工夫で防カビ効果を長持ちさせる
防カビ結露対策工事を行っても、湿気管理が不十分だと、壁紙が剥がれるリスクが残ります。
以下のような「住み方の工夫」を併用することで、施工効果を長く保つことができます。
※住み方の工夫とは、空気の循環と乾燥を言います。
・入浴後は浴室ドアを閉め、浴室内換気扇を8時間以上運転
・洗面所に換気扇が無い場合は、据え置き型除湿機を設置し強制除湿
※湿度計を設置し、60%を超えたら除湿機を稼働
・タオルや棚を壁から5cm以上離して配置
これらを実践するだけで、カビの再発スピードは半分以下になります。
結露を抑える工夫は、防カビ工事と同じくらい重要です。
■まとめ
浴室ドアを開けっぱなしにする習慣は、見えないところで湿気を呼び込み、壁紙裏のカビを育ててしまいます。
カビを止めるためには、「防カビ工事だけでは不十分」という認識が大切です。
結露を抑え、空気を動かし、湿度を管理する。
この3つの要素がそろって初めて、防カビ工事の効果が最大限に発揮されます。
プレモでは、施工と同時に住み方の工夫などの改善提案も行い、「再発させない暮らし方」をお客様と一緒に作っていくことを大切にしています。
----------------------------------------------------------------------
有限会社プレモ
〒362-0062
埼玉県上尾市泉台3-17-28
電話番号 : 048-793-7148(担当:山田)
----------------------------------------------------------------------